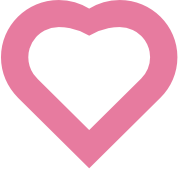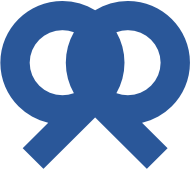ムーブメントと「福祉」
夏野菜の植え付けの季節なので週末は大変です、畑を耕し、畝を立て、苗を植え、支柱
を添えていきます。春の陽ざしが心地よくいい汗をかき、今年もなんとか半分ほどできました。
福祉も新年度がはじまり、どんな1年になるのかと思いを広げて、福祉に関わる変わってきたことを書き出してみました。
①障害者も働いて自立することが当たり前になる。
平成18年に「障害者自立支援法」が制定され、障害者も就職して働くことが推奨されました。それまでは障害のない方と距離を置いて、山里の施設などで独自に生活することが一般的でしたが、障害があっても働いて町で普通に生きることができる制度になりました。
②女性も働くことが当たり前になる。
「仕事と家庭の両立支援制度」が作られ、妊娠、出産、育児に関する支援制度が制定されました。それに伴って就業規則の改定などで就業時間の厳守などから働き方の見直しが進んでいます。奈良県は専業主婦率が全国1位です、逆に働きたい主婦にとっては、適した職場が少ないことが困りごとです。
③社会的養護について「里親制度」が改正される。
養護施設は18才まで入居できますが、社会性の発達や退所後の就職や進学など社会的自立が課題になっています。新たに家庭と同様の環境における養育の推進が明記され、児童相談所の業務も里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した内容になり、継続した支援も考慮して家庭に近いファミリーフォームや里親制度に移行してきています。
④奈良県が観光事業に取り組む。
5年前に平城京遷都1300年祭が盛大に行われましたが、意外と住民や県内企業は消極でした。観光客が増えると交通渋滞になり、ゴミが増えるので困るとの声をよく聞きました。データでも平成18年の奈良県の観光客数は、3,500万人でしたが、観光事業に取り組むと、平成27年は4,146万人で、この10年で18%増加しました。報告書も海外へのプロモーション、春日大社の式年造替などを要因にしており、また大型ホテルの建設計画が増えてきています。
多様な価値や生き方が提唱され、それに応じて制度や施策が実施されると、福祉の現場にも影響がでてきます。主婦や主夫が共に働くことで子育てや学習支援をする仕組みが求められます。社会的養護についても、中高生のときに心身の発達や進学及び就職に向けた支援の充実が必要になります。「福祉」は現実の生活がすべてなので、制度を理解し、未来の可能性を信じて進んでいきたいと考えています。