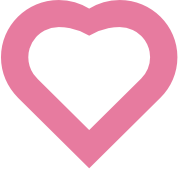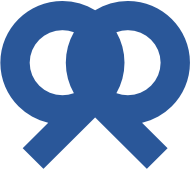福祉の職場作り
5月の連休が過ぎると新入社員の皆さんが、早期に退職されるとの報道があります。退職の理由は多々あると思いますが、Ⅰヶ月でしかも新人研修などがあれば、実際に職場に配属された期間はわずかだと思われます。そこで退職を決めることはある意味で勇敢であり、また決断の早さに驚きを感じます。人にはそれぞれ育ってきた経緯から作られる価値観がありますので、直感的であってもどうしても受け入れることが、できないこともあるとは思います。
人に適した職場について考えてみたいのですが、企業や団体に就職し、配属された部署の業務を担うことになり、同僚や先輩上司の方と協力して目標達成のために共同で取り組むことになります。その関係性を新たに作り上げる前に、退職の結論を出すにはいささか早計のようにも感じます。
昨今、会社は誰のものですか、この議論が頻繁に議題になりますが、法律上は株式会社であれば多数を持つ株主や経営者になりますが、運営しているのは組織なので、それを担っている職員のものとなります。だれしも自分のものは他のものより大切にしますので、組織や職場が自分のものあり、それをよくするのも悪くするのも自分次第になります。もちろんよくする価値もないと判断することもありますが、事前に調査して入社のために就職活動をしたのであれば、その時点では自分の価値観に合うと判断したと思うことができます。
社会福祉法人は株式会社と違って、理事長(経営を担当)のものでもなく、株式はないので株主はいないので、職員のものになります。大きな視点で言うならば、社会福祉法人は社会福祉の充実にために活動する法人格なので、社会のものになることになります。そのために職員は自主的に福祉業務を担いますので、緊急時を除いて誰かに命令されて業務を行うことはありません。職場は自分も参加してされに良いものにすることになります。
例えば、育児休暇については、制度で定められている期間、女性も男性も取得しています。毎年数人の方が利用していますが、その間はみんなで協力して現場の業務を遂行しています。また健康管理についても、企業団体の生命保険に加入することで、もしも職員が三大疾病になることがあっても、対応できる準備をしています。
職場は誰かのものではなく、誰もが役割を担うことで自主的に改善することが。これからの時代には必要なことだと考えています。